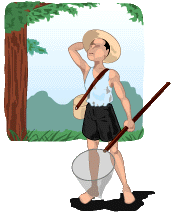けんちゃんが見つけてきた鍾乳洞は、五十崎町内にあった。とはいっても、池窪というかなり山奥なので、大川の鍾乳洞へ行くのとそんなにかわらない。しかし、けんちゃんの話では、ほとんど人が入ったことのない鍾乳洞のため、きれいな状態で残っているそうである。それは、入口が小さいこと、そして、縦穴だったからである。だから、一般の人は入れず、ほとんど手つかずの状態で残っているというのである。多少の危険もあったが、慎重なけんちゃんが大丈夫と言うなら、問題は感じなかった。さっそく遠征隊が結成され、鍾乳洞探険が計画されることになった。この遠征隊には池窪の子どもがいた。けんちゃんの従兄弟だという力持ちのたかちゃんである。このたかちゃんも、けんちゃんなみの自然児であった。
たかちゃんの案内で池窪鍾乳洞のすぐ下まで来て自転車を停めた。大きな崖があってその中腹を指さしたかちゃんは、「あすこに鍾乳洞がある。」と言った。登っていくと確かに穴のようなものが見えてきた。この入口の穴は子どもがやっと入れるくらいの大きさである。この崖が崩れてはじめて、鍾乳洞の入口が開いたのであろう。だからほとんどの人はこの鍾乳洞のことを知らないわけだ。
でも、問題は縦穴であった。入口からのぞくと入口のすぐ下に2〜3人の入れるくらいの空間があり、その下にある広い場所には、入口の下の空間から垂直に7mくらい下りる必要があった。けんちゃんとたかちゃんは、垂直に下りる高さを葛で計測すると、森に入り、肩幅ほどの丈夫な木ぎれを探すように言った。そして彼らは、手頃な太さの葛を集め始めた。そして、探してきた木ぎれと蔦を使って、あっという間に縄ばしごを作ってしまった。それを持って入口から入り、けんちゃんとたかちゃんの見事なコンビネーションで、固定した後、下の広場に垂らした。
 力持ちのたかちゃんが縄ばしごを支え、身の軽いけんちゃんがするすると下りていく。縄ばしごは、少々短かったが、ひょいと飛び下りる。ろうそくを一本灯すと、幻想的な空間が浮き出てきた。わくわくしながら、慎重にみんなが下の広場に次々と降り立った。そして、すばやくいくつかのろうそくをつけた。すると、私たちの口々から歓声が起こった。下こそ粘土状の土だったが、壁も天井も純白の壁である。鍾乳石や石筍、石柱は、できたまんまの美しい姿であった。私たちは、夢中になって観察した。今回の探険では、鍾乳洞をよごさないように、私たちは、灯りを松ヤニではなくろうそくとし、各自できるだけたくさん家から持ってきたのであった。
力持ちのたかちゃんが縄ばしごを支え、身の軽いけんちゃんがするすると下りていく。縄ばしごは、少々短かったが、ひょいと飛び下りる。ろうそくを一本灯すと、幻想的な空間が浮き出てきた。わくわくしながら、慎重にみんなが下の広場に次々と降り立った。そして、すばやくいくつかのろうそくをつけた。すると、私たちの口々から歓声が起こった。下こそ粘土状の土だったが、壁も天井も純白の壁である。鍾乳石や石筍、石柱は、できたまんまの美しい姿であった。私たちは、夢中になって観察した。今回の探険では、鍾乳洞をよごさないように、私たちは、灯りを松ヤニではなくろうそくとし、各自できるだけたくさん家から持ってきたのであった。
そのうち、「ろうそくをたくさんつけてみよう。」と、だれかが言った。それはいいと、みんなは、ろうそくに次々と火を点け、各所に設置した。ろうそくが数十本もともされると、真っ白な壁に反射されて、広場は光の宮殿になった。私たちは時間の過ぎるのも忘れて、王様になったような気持ちで、その宮殿の美しさを楽しみ、至福のときをすごしたのだった。私が最も気に入ったのは、人がやっと入るくらいのくぼみにあった、樹氷のミニチュアのような石筍?である。雪のように真っ白な1cmほどの樹氷は、それぞれがくぼみの一面に無数に連なり、砂糖菓子のようにキラキラと輝いていた。鍾乳石も大きいのはそれなりに迫力があるが、小さいものは、氷のように蒼く透き通って、結晶がきれいだった。それぞれが自分の見つけたきれいな鍾乳石を指さして自慢する。私が、自然の美しさを意識したのは、このときが最初だったかもしれない。
そのうち、だれかが「もう外は暗くなりよるぞ。」と言った。その言葉で、時間を忘れていた私たちは、はっとして、帰る準備を始めた。そして、各人一個という約束で記念品として人差し指ほどの小さな鍾乳石を採取してポケットに押し込んだ。そして、ろうそくを回収し、私が最初に縄ばしごに飛びついた。次に縄ばしごにぶら下がって、上の段に手を伸ばそうとした。しかし、このとき私は、身体の異常に気がついたのだった。
力が出ないのである。何度か繰り返した後、「力がでんけん、登れん。」と言って飛び下りる。たかちゃんが次に登ろうとする。「ほんとや、力がでん。」とたかちゃんもびっくりしている。縄ばしごは、足の部分が不安定に動いて、普通のはしごを登るよりもコツと力が必要であるが、それにしてもどうしたのだろう。そのとき私は、はっと気づいた。「ろうそくよ。ろうそくをつけまくったけん。酸素が少なくなったんと違うか?」他の子もそれに気づいて青ざめ、急いで一本を除いてろうそくを消した。それまでのお楽しみの時間は、一転してサバイバルの場面となったのである。
私たちはいろいろと考え、順番にチャレンジした。助けを呼ぶのも、人家から遠く離れた崖の中腹から聞こえるはずもないし、時間が経つほど酸素は少なくなる。考えた末に、私たちは身の軽いけんちゃんを、みんなでなんとか縄ばしごに押し上げた。けんちゃんは、それで上の段に上ることができた。次は、たかちゃんが私を押し上げて、けんちゃんが上から引っ張り上げた。少々強引な方法ではあったが、最後のたかちゃんを引っ張り上げたときの充実感は、忘れられない。手を取り合って喜んだものである。私たちは命からがら穴の外にはい出したとき、外はもう真っ暗だった。
「ここのことはだれにも言うなよ。言うと荒らされるかもしれんけん。ここは僕らだけの秘密の宮殿じゃけん。」と互いに約束して、一目散に帰路についた。家では叱られたと思うが覚えていない。記憶に残っているのは、記念に持ち帰った鍾乳石である。これをながめながら、あの夢のような体験を思い起していたのであった。
それから一ヶ月ほどたったある日、たかちゃんが、「あの鍾乳洞があらされているらしいぞ」と言ってきた。さっそく、私たちはそのうわさを確かめるために、二度目の鍾乳洞探険を行った。ドキドキしながら、縄ばしごを下った私たちは、ろうそくに火をつけた。するとどうだろう。鍾乳石や石筍はほとんどがたたき折られ、壁は多くの傷が残り、どろどろに汚されている。小さな鍾乳石やミニチュアの樹氷もおもしろ半分に破壊され、もう、自然の美しさといった感じはない。きわめて悪質な、明らかに悪意の感じられる破壊の仕方だった。私たちは、「だれかがこの鍾乳洞のことをしゃべったんじゃないか。」と口々に言った。しかし、だれも困惑の表情である。
結局、その後もこの破壊がだれの手によるものか、誰が原因なのかまったくわからなかった。宮殿のようにきれいだった鍾乳洞は、今や破壊の殿堂になってしまったのである。私は、家に帰って、自分の持ち帰った小さな鍾乳石を手にとって見た。あれだけきれいだった鍾乳石も、なぜかそのときは色あせて見えた。そのうち、たった一つではあるが、鍾乳石を持ち帰ったことに、後ろめたいような気持ちがしてきて、隠すようにたんすの小さな引き出しに入れた。そしてその後、この引き出しが開かれることはなかった。また、一緒に行った仲間も、鍾乳洞のことを話題に出すことはなくなった。それが、私たちが人間による自然破壊を意識した、最初のときだったのだろう。